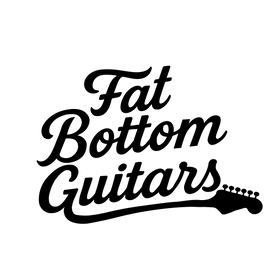トム・ウェイツは現代音楽界で最も謎めいた存在の一人です。ウイスキーに浸ったバラードやスモーキーなジャズの哀愁から、実験的なノイズコラージュ、シュールでシアトリカルなロックまで、彼のサウンドは独自の世界を形成しています。50年にわたるキャリアを通して、ウェイツはピアノバーで歌い上げるしわがれた声の詩人から、楽器、声、そしてファウンドサウンドをまるで画家が筆を振るうように操る、サウンドの作家へと進化を遂げました。その変貌の中心には、ウェイツ自身だけでなく、彼のビジョンを具現化するために尽力した並外れたミュージシャンたち、そして彼らが使用した特別な機材の存在があります。
初期:バースツール、バラード、そして失恋
1970年代、トム・ウェイツはランディ・ニューマンやハリー・チャピンといったシンガーソングライターと同列に扱われることが多かった。 『Closing Time』 (1973年)や『The Heart of Saturday Night 』(1974年)といったアルバムは、ピアノ、ダブルベース、ブラシドラムを軸とした、ジャズ風の柔らかな楽曲が特徴的だった。ギターはこの時期、脇役的な役割にとどまり、通常はアコースティック・リズムギターがクリーンでミニマルな音色で録音されていた。ウェイツの初期のアコースティック作品は、以下のような楽器の自然な音色に重きを置いていた。
-
Martin 0-15 :温かみのある中音域とブルージーな重低音で知られる、小ぶりなボディのマホガニー材アコースティックギター。ストーリーテリングに最適です。
-
Gibson L-1 : 箱型のビンテージ風の特徴を持つ大恐慌時代のアコースティックギター。
アレンジは比較的従来通りではあったが、ウェイツが限界に挑戦し、予測不可能で不完全なものを求めていることがすでに感じられた。
ソニック・シフト:ソードフィッシュトロンボーンズ以降
1983年、ソードフィッシュトロンボーンズで全てが変わった。トムはメジャーレーベルの期待を振り切り、未知の領域へと突き進んだ。ジャンクヤード・パーカッション、歪んだボーカル、傷ついたホーン、弓で弾くノコギリ、ポンプオルガン、そして奇妙なギターのテクスチャが、忘れがたいと同時に爽快な美学を生み出した。
そして、この改革の中心にいたのはギタリストのマーク・リボーだった。
マーク・リボー:クラッターの建築家
『Rain Dogs』 (1985年)、 『Frank's Wild Years』 (1987年)、 『Mule Variations』 (1999年)、 『Real Gone』 (2004年)、 『Bad As Me 』(2011年)におけるリボーの演奏は、ロックやジャズのどの作品にも類を見ない。彼は単に音符を演奏するだけでなく、登場人物の個性を巧みに表現している。壊れた操り人形、吠える犬、錆びた汽笛など、リボーのパートは深い物語性を持っている。
彼は、自分が求める荒々しさと予測不可能なサウンドを得るために、質屋で買った安物のエレキギターをよく使っていた。彼の機材は意図的にローファイだった。
-
Teisco Del Reys、Silvertone および Harmony ギター: マイクロフォニック ピックアップと不安定なチューニングで知られています。
-
Fender Deluxe Reverb アンプ: 自然な歪みになるように音量を上げます。
-
ミニマリスト ペダルボード: 多くの場合、ファズとディレイまたはトレモロだけです。
リボットは限界を受け入れた。 『レイン・ドッグス』について彼はこう語った。「トムは、メキシコのバーの裏の路地で見つけたような、古くて奇妙なサウンドにしたかったんだ。」
「Clap Hands」でのぎざぎざのスタブ、「Jockey Full of Bourbon」での沼地のようなリフ、「Tango Till They're Sore」でのマリアッチ風のセンスは、どれも完璧さではなく雰囲気に敏感な演奏家であることを示している。
その他のコラボレーター:ブルース、ビーフ、ビザール
キース・リチャーズ
ローリング・ストーンズの伝説的人物は、 『レイン・ドッグス』(「ビッグ・ブラック・マライア」)や、後に『バッド・アズ・ミー』で、ルーズでレザーのようなギターを演奏し、同作の複数の曲で演奏している。彼の紛れもないトーン(しばしばテレキャスターをオーバードライブしたアンプに最小限のエフェクトをかけた音色)は、ウェイツの混沌とした本能に揺るぎない自信を与えた。
デビッド・イダルゴ(ロス・ロボス)
ヒダルゴは『Bad As Me』でギター、アコーディオン、バイオリンを演奏し、実験的なアレンジメントに素朴な質感を重ねた。
ジョー・ゴア
長年ウェイツのサイドマンを務め、ヴィブラートアーム、原始的なファズボックス、そして奇妙なチューニングを駆使して実験的なトーンを生み出した。使い古されたフェンダー・ジャガーとヴィンテージの日本製ギターを愛用していた。
ウェイツ自身の手によるギター
ウェイツは主にボーカリストとピアニストとして知られていますが、特にライブパフォーマンスではギター演奏が彼の個性の中心となっています。
彼のギアの選択は、使い古されたものや忘れ去られたものに対する彼の愛情を反映しています。
-
Danelectro 5005 Convertible :多くの演奏で使用されている安価なホローボディのアコースティック・エレクトリック。薄く、ドライで、パーカッシブなサウンドが特徴です。
-
Gretsch New Yorker アーチトップ: まろやかで箱型のサウンドを備えたビンテージ アコースティック エレクトリック。
-
Harmony H44 Stratotone : シングルカットのミニマリスト ブルース マシン。
-
Gibson Hummingbird : よりメロディアスなアコースティックナンバーに使用されます。
彼はメガホンや歪んだマイクを通して歌うことが多く、ザラザラとしたローファイなキャラクターを醸し出している。ライブでは、ファノンMP5の警察用拡声器に向かって吠えたり、古いバレットマイクを両手で抱えてセリフを唸り声で歌ったりする姿を目にするかもしれない。
レコーディングテクニック:ジャンクヤードオーケストラ
ウェイツのレコードは、演奏だけでなく、その録音方法でも有名です。特徴的なアプローチをいくつかご紹介します。
-
ライブ マイク ブリード: 楽器の音が互いのマイクに漏れて、より「広々とした」サウンドが生まれます。
-
Neumann U47 および Sony C37 マイク: それぞれボーカルとピアノに使用され、ビンテージの温かみが高く評価されています。
-
リボン マイク(RCA 77-DX など): ふんわりとしたノスタルジックなトーンを実現します。
-
1081 プリアンプ搭載の Neve 8048 コンソール: 厚みのある音楽的な EQ シェーピング。
-
見つかった打楽器の音:ホイールキャップ、ドアフレーム、ラジエーターパイプ、マリンバ、ブレーキドラム。
ウェイツはかつてこう言った。「私は、楽器店では必ずしも見つからないような音を出すものが好きなんです。」
狂気へのメソッド
ウェイツは技巧性にはこだわらない。彼が大切にしているのは、ヴァイブスだ。彼は、湿っぽい地下室にいるか、午前2時のカーニバルの外にいるか、あるいはひび割れた蓄音機の中に閉じ込められているかのような感覚を、聴衆に味わわせたいのだ。機材は、そのための手段に過ぎない。何もかもが綺麗だ。全てに歴史がある。
彼の音楽には幽霊が棲みついている。そして、安物のギター、錆びたマイク、オーバーロードしたプリアンプはすべて、幽霊を招き入れるもう一つの方法なのだ。
結論
トム・ウェイツのサウンドは、狂気と魔法のモザイクだ。それは彼自身の唯一無二のビジョンだけでなく、機材や共演者たちにも大きく負っている。壊れたギターやローファイなマイクから、マーク・リボーのざらついた輝き、そしてキース・リチャーズの闊歩さまで、機材は不完全さを高尚な芸術へと昇華させた男の物語を物語っている。
磨きに夢中になっている世界において、ウェイツは私たちに、ひび割れの中にも美しさが見つかるということを思い出させてくれる。